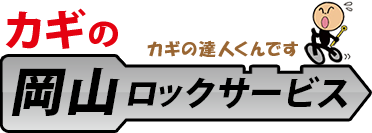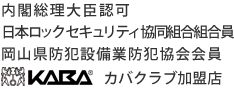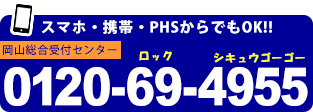賃貸物件に入居する際、鍵の交換費用として「初期費用」が請求されます。
入居時の鍵交換費用の一般的な目安は、10,000円から20,000円程度ですが、高機能の鍵の場合は、費用は20,000円から30,000円程度になる場合があります。ただし、鍵交換費用を支払う法的義務はありません。
鍵の交換費用を交渉して減額できることをご存知でしょうか?また、鍵が使いにくい場合は、ご自身で交換することも可能です。
本記事では、鍵の交換費用の確認方法と交渉ポイントなどについて解説していきます。
鍵の交換とは何?

鍵の交換とは、玄関の鍵とシリンダーを交換する作業です。退去時や入居時に、前の入居者の不法侵入するリスクを防ぐために、鍵を交換する一般的な慣行です。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、鍵の交換費用は貸主が負担すべきとされています。ただし、これらのガイドラインは、法的拘束力がないので、多くの場合賃借人が費用を負担することになります。
鍵の交換費用は通常、10,000円から30,000円程度で、初期の引越費用に含まれていることが一般的です。また、ガイドラインでは、貸主が費用を負担すべきとされていますが、状況によっては交渉の余地があります。
初期費用が高額だと感じる場合は、以下の交渉テクニックをご参照してください。
鍵交換費用は本当に必要?
ほとんどの不動産物件では、「防犯上の理由」から、入居時に鍵交換を行うのが一般的です。前の入居者が合鍵を持っているリスクを防ぐため、鍵を新しくしておくことは、オーナー側にとっても借主にとっても安心材料となります。
ただし、法律上、鍵交換費用を借主が負担しなければならないという義務はありません。 したがって、事前に交渉して費用を抑えることは十分可能なのです。
賃貸物件の鍵交換費用の交渉テクニック

鍵の交換は一般的に任意のため、費用の削減を交渉可能です。まず、国土交通省のガイドラインを提示して、不動産仲介業者を通じて、大家さんと交渉して、費用を負担してもらえるかどうか確認してください。
拒否された場合、すぐに引っ越すことを提案すると効果的です。大家さんが全額を負担しない場合でも、一部負担や割引を交渉できる可能性があります。
特に、6月から8月と11月から2月は賃貸需要が低いので、賃貸契約を締結するのが困難な時期です。そのため、多くの大家さんは入居者を確保するために、わずかな割引を提示する傾向があります。
これらの期間中に、鍵の交換費用を交渉することは有効です。そのため、交渉のタイミングを慎重に検討することをおすすめします。
鍵交換費用の確認方法と交渉ポイント
契約を締結する前に、鍵の交換費用の取り扱いについて徹底的に確認することが重要です。具体的には、賃貸借契約書や重要事項説明書に、鍵の交換費用に関する規定が含まれているかどうかを確認してください。
文書には、費用の負担者、金額、支払いスケジュールが明確に記載されている必要があります。不明点や曖昧な表現がある場合は、お気軽に当社の担当者に問い合わせてください。
提示された金額に納得できない場合は、交渉も選択肢のひとつです。例えば、「費用はできるだけ抑えたいので、一部負担していただけませんか?」など確認しましょう。
また、長期滞在の予定があることを相手に伝えることで、より協力的な対応が得られる場合もあります。交渉が難航して、解決が難しい場合は、宅地建物取引業協会や消費生活センターなどの相談機関を利用することもできます。
契約内容に不当な条項があると思われる場合は、消費者契約法が適用される場合があるので、安心のために専門家に相談することをおすすめします。
鍵の交換費用を抑えるためのポイント

まず、見積もりの依頼後に、見積価格と相場を比較することが重要です。同じ様な作業でも、業者によって費用に大きな違いがある場合があります。そのため、見積もりを受け取った後は、必ず相場と比較してください。
一部の業者は、鍵交換を含む割引パッケージを提供しています。例えば、鍵交換を含むセットプランや、オンライン申し込みで割引が適用されるキャンペーンなどです。
もう一つの選択肢は、繁忙期を避けることです。繁忙期には、サービス業者が人手不足になり、料金が高くなる可能性があります。逆に、閑散期には、より手頃な料金でサービスを利用できる場合があります。
鍵の交換を自分で行うことは可能ですが、無断での交換は契約違反とみなされ、トラブルの原因となる可能性があるので、注意が必要です。
まとめ

賃貸借契約時に発生する基本的な鍵交換費用は、鍵の種類、作業範囲、場所、タイミングにより異なり、数千円から数万円、場合によっては10万円を超えることもあります。
これらの費用の負担者は、契約内容により決定されるため、事前に確認することが重要です。懸念がある場合は、見積もりを比較して交渉したり、繁忙期を避けて費用を削減するなどの対応が可能です。
また、契約手続きをスムーズに進めるために、事前の確認と準備が不可欠です。