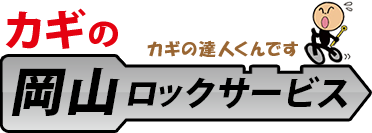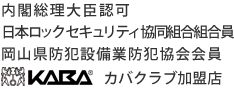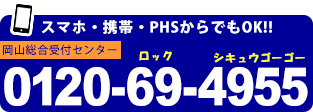本記事では、カードキーの種類やカードキーに交換するメリット・デメリット、故障時の対処法について詳しく解説します。
鍵の種類の中で注目のカードキーとは何?

カードキーとは、物理的な鍵の代わりにカードを使って、扉の開け閉めを行う電子錠システムのことです。従来の金属製の鍵と鍵穴を使った方式とは異なり、鍵穴が存在しない、もしくは補助的に使われるだけの設計になっております。
また、住宅やオフィス、ホテル、公共施設などで広く導入されています。
これまでの様に、鍵穴に合鍵を差すのではなく、カードキーはドアを開閉できるキーレスな電子錠の一種です。主にタッチ式と挿し込み式の2タイプがあり、それぞれ鍵としての利便性や使い勝手に特徴があります。
タッチ式カードキー
非接触ICカードをかざすことで、解錠する方式です。カードリーダーにカードを近づけるだけで解錠できるので、スムーズなドア開閉が可能です。SuicaなどのICカードやスマートフォン(おサイフケータイ)に設定できるタイプもあり、財布からカードを探す手間を省けます。
挿し込み式カードキー
磁気テープや穴あき構造など、カードに読み取り用情報があるタイプです。専用の挿入口に差し込む方式で、アナログな仕組みで動作しますが、非接触ICの普及により採用率は減少しつつあります。
一戸建て向きのカードキーの種類

一戸建て住宅ではさらに、カードキーには「接触式」、「非接触式」の大別があります。接触式はカードを差し込んで鍵を開ける方式であり、複数カード登録や、通常の鍵との併用が可能です。一方の非接触式はかざすだけで解錠し、より簡便な操作性が特徴です。
カードキーは2つのタイプに分類される
カードキーは大きく「差し込むタイプ」と「かざすタイプ」の2通りの操作方式に分類できます。それぞれに利点と欠点があり、防犯性や日常の使い勝手に影響します。
差し込むタイプの分類
挿入口にカードを入れることによって、鍵が開きます。ただし非接触ICの普及により、徐々に設置数が減少しています。
こちらのタイプには、以下の3つがあります。
- アナログカード:穴を読み込む方式
- 磁気カード:磁気テープで情報を読み取る方式
- ICカード:内部にICチップを搭載
中でも磁気カードがもっとも広く使われています。
かざすタイプの仕組み
データの読み取り装置にカードをかざすことで、非接触ICカードの仕組みを利用して解錠します。差し込む手間がなくて、スムーズな開閉が可能です。Suicaなど他のICカードやスマホを利用できる製品も増えています。
カードキーに交換する4つのメリット

次に、カードキーに交換する4つのメリットについて解説します。
1. 鍵の操作がスムーズに
かざすタイプであれば、カードを近づけるだけで、鍵の開閉ができます。物理的なキーの様に差し込む手間が不要なので、荷物を持ったままでもスムーズに操作できます。
また、オートロック機能付きの製品であれば、ドアを閉じるだけで自動で施錠され、防犯性も向上します。
持ち運びしやすい
カードキーは、一般的にクレジットカードや免許証と同じサイズで設計されているので、財布やパスケースに入れて持ち運べます。さらに、おサイフケータイ機能付きスマホや、交通系ICカードに設定可能なタイプであれば、専用カードすら持ち歩く必要がなくなります。
ピッキング対策に有効
カードキーには、鍵穴が存在しないので、ピッキングによる不正解錠が不可能です。一部の製品では、非常時に備えた物理キーも用意されていますが、そちらの場合は高防犯性のディンプルキーが採用されることが一般的です。
合鍵を勝手に作られない
カードキーは、製造元でのみ複製可能な構造のため、第三者による合鍵作成が困難です。自分で管理を徹底すれば、不正利用のリスクを大きく下げられます。
カードキーが故障した場合の対処法
自力での修理はおすすめしません
カードキーが反応しない・動作しないなどのトラブルが起きた場合、電気的な構造が絡むことも多く、知識がない状態での自己修理はさらなる故障を招く可能性があります。
専門の鍵業者へ相談しましょう
カードキーが使えなくなり、家に入れない状況に陥った場合には、24時間対応可能な鍵業者へ早急に連絡しましょう。「カードキー非対応」「予約待ち」「営業時間外」などの理由で断られるケースもあるので、カードキー対応・即日対応・24時間受付の業者を選ぶと安心です。
まとめ

カードキーは、従来の金属製の鍵に比べて操作が簡単で、盗難・複製リスクの低い選択肢です。非接触で使えるタイプは、特に利便性が高く、ICカードやスマホとの連携も可能です。
一方で、電子機器であるので、故障時の対応や初期設定には専門知識が必要です。トラブル時には、鍵業者への依頼を前提に、信頼できる業者を日頃からチェックしておくと良いでしょう。
また、鍵のスタイルを見直すことで、暮らしの安全性と快適さを両立させる第一歩になります。